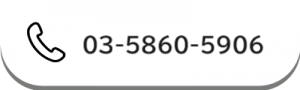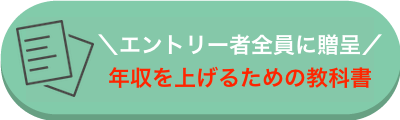株式会社バーチャルキャスト・岩城 進之介氏が語る VRビジネスの今後と求められる人材像

目次
『エンタメ人』がお届けする、エンタメ業界のトッププロデューサー/経営者へのインタビュー連載。エンタメ業界へ転職を考えている方へ向けて、若手時代の苦労話から現在の業界動向まで伺っていく。第24回は、VRシステムの開発・運営・企画を行う会社を取り上げる。(編集部)
岩城進之介
株式会社バーチャルキャスト・CTO
ドワンゴにおいて各種AR・VR・放送技術・イベント演出のシステム開発を手掛け、バーチャルキャラクターが出演するイベント等を数多く送り出した。2018年、株式会社バーチャルキャストを設立。技術面の指揮にあたっている。
アバターをサービス横断で使用できるようにする3Dアバターファイルフォーマット「VRM」を開発・提唱、VRMコンソーシアム理事・技術委員長。
「ちょっと間違った未来をつくる」に込めた想い

── 御社の事業内容について教えてください。
私ども、株式会社バーチャルキャスト(以下、バーチャルキャスト)は「ちょっと間違った未来をつくる」をテーマとして、VRの世界で人とコミュニケーションをするライブエンターテインメントサービスを展開しています。
具体的に言うと、VRのアプリケーションとサービスを開発している会社です。
──「ちょっと間違った未来をつくる」というのは、かなりユニークなビジョンだと思います。どのような想いで作られたのでしょうか?
今、FacebookがOculusという会社を買収して、VRの世界を牽引しています。しかし、こういった企業がつくるサービスは、どうしても欧米の価値観に基づいた世界を目指しているように思います。
これは、VRに限らずWebの世界もそうです。もちろん、それは正しいのですが、その一つの世界観だけで、全ての世界が塗りつぶされてしまうというのは面白くありません。
たとえ、ほかの人から見てちょっと間違っているというように見えても、面白い世界観、楽しい空間というものを残していきたい。ちょっと面白い、一風変わった価値観というものに居場所を与えたいというのが一つの大きな目的ですね。
── なぜ、VR領域に参入していこうと思われたのでしょうか? バーチャルキャストサービスの立ち上げの経緯についてお聞かせください。
もともと、株式会社ドワンゴ(以下、ドワンゴ)でVR・AR領域の開発を担当していたところ、2018年にバーチャルYouTuber(VTuber)という存在が急激に盛り上がったんです。
そこで、このムーブメントにうまく合致するサービスの立ち上げが求められ、VRでの生放送を実現するサービスをつくろうということになりました。当時、ニコニコ生放送でVR・ARシステムを開発していた、株式会社インフィニットループと共同で立ち上げたVRライブ・コミュニケーションサービスが「バーチャルキャスト(Virtual Cast)」です。
VRがなかなか普及しないワケとは?

── 今後、VR・ARはどのように普及していくと予想されていますか?
VRは盛り上がると言われだしてからもう何年も経ってるのですが、コミュニケーションツールとして大きな可能性がある、と私は思っています。
とくに今、人と直接会うことが難しいご時世です。しかし、人とコミュニケーションを取りたいという人たちにとって、VRの価値は高いのではないでしょうか。スマートフォンのような「切り取られた窓を通して見る世界」とは違って、VRは同じ空間の共有を可能にするので、ようやくVRの時代がやってくるのではないかなと。
── VRの普及において、どういった点が課題となっているのでしょうか?
「ながら利用」が難しいところですね。
スマートフォンでコミュニケーションを取りながら、別のことをするというシチュエーションは非常に多いです。並行して何かいろんなことをするというのは、現代人は当たり前にやっていますよね。
しかし現状のVRだと、一つのアプリケーションで世界が全部塗りつぶされてしまい、「ながら利用」が難しい。もう少し気軽にVR空間の中で「ながら利用」ができるようになれば、一気に普及するのではないかなと思っています。
ヘッドマウントディスプレイ(頭部に装着することでVR体験ができる装置)も、やっぱり着脱が面倒くさいというのがありますよね。着けっぱなしのまま、その空間の中で日常生活を送ることができれば、みんながその便利さに気付くのではないかなと思います。
── 今後VRビジネスを展開していく上で解決していきたい社会課題があればお聞かせください。
やはり距離の解決。人とのコミュニケーションですね。
── やはり去年からのコロナウィルスの流行で、エンタメ業界自体のあり方もかなり変化があったと思います。「人との距離」というキーワードがありましたが、そのほかどういう点で変化を感じられますか?
コロナに関係なく、エンタメの世界は定期的に、同期と非同期を行ったり来たりしていると思っています。
「みんなと一緒につながりたい」という欲求に対する手段として、一斉に同じタイミングで同じイベントを体験することでその場のつながりの感覚を得る。その一方で、「時間を拘束されるのが嫌だから、みんなと時間をずらして好きなことをしたいんだ」という非同期の欲求がシーソーのように行ったり来たりしていると。
リアルにみんなで同じ場所に集まって大きなイベントをするのがすごく楽しい!という時期にコロナが直撃して、みんなフラストレーションが溜まっているという状況だと思っています。
── 今後コロナについては長期化の懸念もありますが、1年後あるいは数年先の未来についてどのようにお考えでしょうか?
今、リアルのイベントをどうネットワーク越しに再現するかというところで、みんないろいろ試行錯誤しているところです。
ドワンゴ時代の、ニコニコ生放送でのコメントを使った同期コミュニケーションというのは、かなりうまくいっていたと思っていて。その上でさらにもう一つ上のつながりができないか、というのをみんなで今試行錯誤しているところです。近い将来、「これだ!」というようなものが見つかるといいなと思っています。
──VR業界の変化について教えてください。
個人で面白いことをやろうというフェーズから、ビジネスのフェーズに入ってきた感じはしますね。
2013年、2014年頃は本当に黎明期で、個人がプロトタイプのようなものをつくって「面白いね」と盛り上がっていましたが、ここ2、3年はきちんとしたプロダクトをつくり上げないと、あまり相手にされないフェーズになってきたなと感じています。
「第一次VRブーム」がキャリアの礎に

── 岩城様がVRに興味を持ったきっかけとは?
1990年代に起きた「第一次VRブーム」ですね。ヘッドマウントディスプレイを使ったVRの仕組みが盛り上がった時期が1回あったんです。「これはすごい!面白い!」と、その没入体験が私にとって興味の中心になりました。
その頃はまだ一介の学生でしたが、いろんなイベントに行ったり、いろんな技術の展示を見に行ったり。「自分でも何かつくってみたい!」と、アトラクションっぽいものを部活でつくったりもしました。
──ドワンゴ入社から、バーチャルキャストCTO就任まで、どのようなキャリアを歩んでこられましたか?
もう10年以上も前の話になりますが、ドワンゴに入る前の会社が業績悪化して、社員全員解雇されてしまったんです。
そこで、Twitterで「転職先募集中」と投稿をして、お声かけしてもらった先の面接を受けながら何ヶ月か過ごしました。残念ながら、受けた先はどこも受からず・・・。
当時、ニコニコ生放送で個人の放送をしていたので、「お断りのメールが来たよ」などと落ち込んで放送をしていたところ、「うち受けに来てよ」というコメントが入ったんです。
その連絡をくれた先がドワンゴで、そのまま採用になって入社したのが2011年1月ですね。最初にニコニコ生放送の開発に入り、その次にはニコファーレなどの開発プロジェクトに参加しました。
ニコファーレは、没入型ライブハウスシステムです。会場内に360°LEDを設置して、そこにコメントを流します。全くの無観客であっても、盛り上がるタイミングでコメントの量が増えると、そのLED表示で周りの景色が明るくなり、人の盛り上がりを体感できるものでした。そこで、ARでキャラクターがライブをするシステムもつくり始め、AR・VRに関するプロジェクトは基本的に私が担当するようになりました。
そして2018年、「バーチャルキャスト」を事業のコアにして新しく会社をつくろうという話になり、バーチャルキャストのCTOにおさまったという感じです。
VR業界で活躍する人材像とは?

── 今後、VRビジネスの市場では、どのような人が活躍していくと思われますか?
やはりまだ、VRの業界は成熟しきっていないというか、どんなに大きな会社のVR部門でもまだベンチャー的な要素があると思っています。
新しい業界ならではの課題がいっぱい転がっているので、言われた仕事をやるタイプではなくて、次々と課題を見つけては解決していくタイプの人が活躍できるのではないでしょうか。
── 課題解決型の人材ですね。御社でも中途採用など人材の募集はされていますか?
積極採用はしていませんが、すごくいい方がいたら、という感じですね。
VRに関していえば、やはり技術のことが分かる人が求められます。技術の限界と可能性、どちらも分かる人。「これはこういう技術を使ってこう組み合わせればできるはずだ! だけど、これはできない!」という、できないのであれば代わりにこうすればきっと面白くなる、みたいな技術の可能性と限界を両方知り尽くした上でプランをつくることができる人が求められますね。
── 変化の激しい業界だと思いますが、岩城様から見てVR業界で活躍されている人に特徴はありますか?
やっぱり、まずは楽しんでる人ですね。技術そのものと、技術がもたらす新しさをまず根っから楽しんでいる人。
あとは、技術一辺倒だとか表現一辺倒ではなくて、両方100%ではなくても、どちらに対してもアンテナを張っている人だと思いますね。
── 業界未経験でも興味があるという人も多いと思うのですが、VR業界に就職するために今日からできることはありますか?
自分で何かつくってみることだと思います。今は、つくるためのツールがいろいろ発達しています。
本当に初心者でも触れる仕組みは全部そろっているので、何かしら自分でつくってみる。既存のアプリケーションを触るだけではなくて、自分で何かつくるという体験から、可能性と限界、両方を知ることができるのではないかなと思いますね。
── 最後に、岩城様にとって「エンタメ」とは何でしょうか?
個人の力をエンパワーメント(能力開花)させるもの、ですかね。「楽しい」というモチベーションが個人の創作の力を加速させると思うので。
私がVR業界に足を踏み入れたきっかけも、やはり最初に触れた没入体験であるエンタメでした。第一次VRブームの頃に、「これはすごい!こういうものを自分でもつくりたい!」という気持ちから、私のキャリアの全てが始まっています。
「楽しい」という気持ちは、人を動かす原動力になると思います。
(2021年4月20日、株式会社バーチャルキャストにて)